相続に関するご相談ならお気軽にご相談ください!
えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
営業時間 | 9:00〜18:30 |
|---|
休業日 | 土日祝 |
|---|
事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。
遺産の範囲はどこまで?
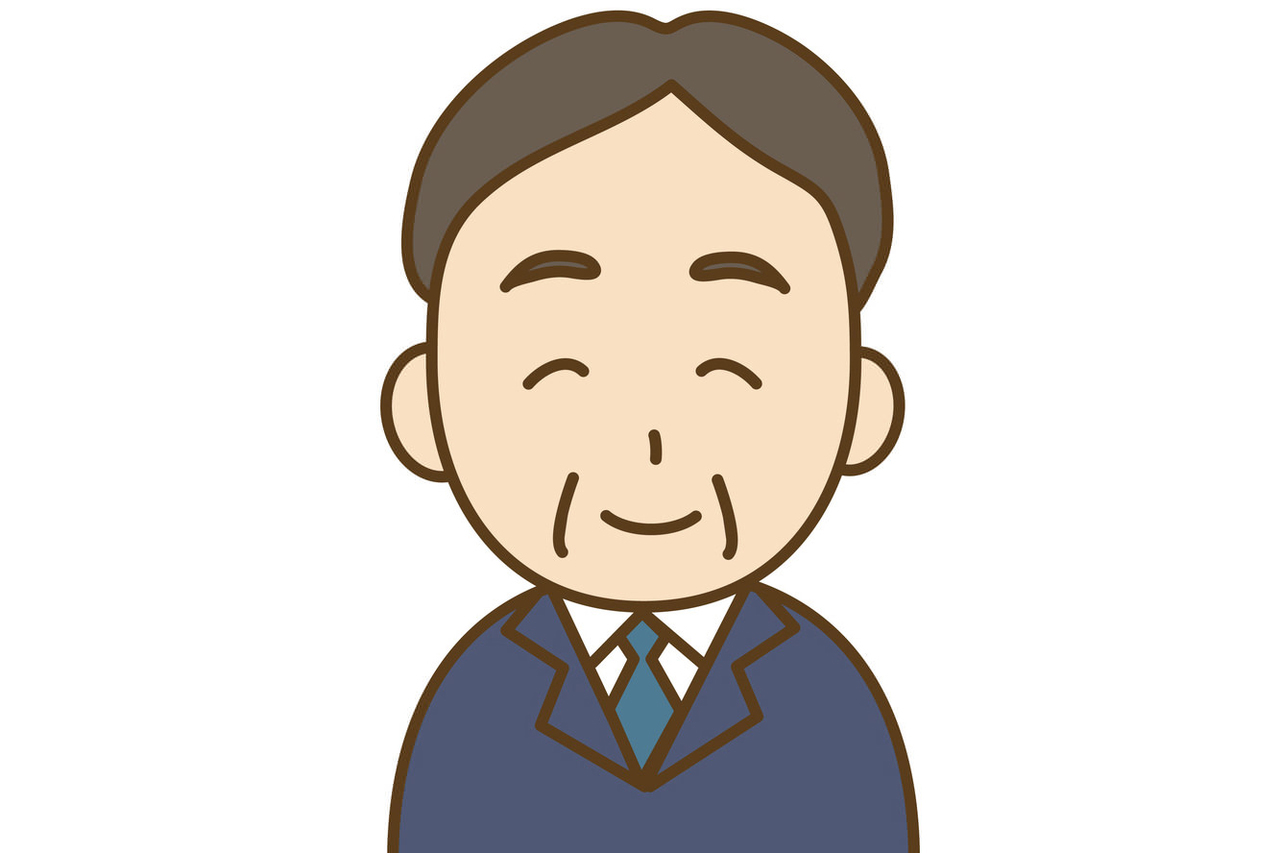
こちらでは遺産分割の対象にならない遺産についてご紹介いたします。。
どうぞご参考になさってください。
また、遺産分割の対象となる遺産について、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。

遺産分割の対象とならない主な財産
遺産分割の対象とならない主な財産は、次のとおりです。
遺産分割の対象とならない主な財産
1.相続が開始してから遺産分割が確定するまでの不動産の賃料(被相続人が不動産の大家さんの場合)
相続が開始してから遺産分割が確定するまでの不動産の賃料については、各相続人が法定相続分に応じた金額を取得します。
したがって、原則として遺産分割の対象となりません。
ただし、法定相続人全員が、不動産の相続が開始した後から遺産分割確定までの不動産の賃料を遺産に含めると合意した場合は、遺産分割の対象とできます。
➡この場合、遺産分割でその不動産を取得する相続人が、相続開始の時(被相続人がおなくなりになった時)にさかのぼって不動産の賃料を取得することになります。
2.生命保険金(被相続人が被保険者の場合)
生命保険金に受取人指定がある場合、基本的に相続財産になりません。
ただし、生命保険金の額が遺産の総額に対して大きい場合、その受取人に対する特別受益として扱われることがあります。
➡生命保険金の受取人指定がない場合、保険契約の約款にしたがって判断しますが、多くの場合、保険契約の約款には相続人に支払うと定められているため、相続人が法定相続分の割合で生命保険金を受け取ることが多いと思われます。
3.死亡退職金
(民間企業の場合)
会社の退職金支給規程で、死亡退職金の受取人が定められている場合、相続財産ではないので遺産分割できません。
会社の退職金支給規程で、死亡退職金の受取人が定められていない場合、相続財産になるか否かは個別に判断することになります。裁判所の判例や審判でも分かれているようです。
(国家公務員の場合)
国家公務員退職手当法によって、死亡退職金の受取人が定められているため、相続財産ではないので遺産分割できません。
(地方公務員の場合)
それぞれの自治体の条例によって死亡退職金支給が定められますが、地方公務員も国家公務員の例に準じるようにとの国からの通達があります。
したがって、相続財産ではないので遺産分割できません。
4.国民年金の遺族基礎年金
国民年金法によって、遺族基礎年金を受け取ることのできる遺族の範囲と遺族の順位が定められています。したがって、相続財産ではないので遺産分割できません。
➡遺族の範囲と順位については、下にご紹介しております「遺産分割と国民年金について」をご覧になってください。

遺産分割と国民年金について
お亡くなりになった方が、一定の条件を満たせば遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。また、労災保険や健康保険から遺族に対して、葬祭給付、埋葬費などが支給されます。
社会保険や労働保険からの年金や給付は、相続財産ではないので遺産分割の対象となりません。
こちらでは、国民年金から遺族に支給される遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金についてご紹介いたします。
遺族に支給される年金・社会保険給付
| 国民年金から支給されるもの | ①遺族基礎年金 ②寡婦年金 ➂死亡一時金 ④未支給の年金 |
| 厚生年金から支給されるもの | ①遺族厚生年金 ②未支給の年金 |
| 健康保険から支給されるもの | ①埋葬料 ②埋葬費 |
| 労災保険から支給されるもの | ①遺族(補償)年金 ②遺族(補償)年金前払一時金 ➂遺族(補償)一時金 ④葬祭料(葬祭給付)⑤未支給の保険給付 |
| 雇用保険から支給されるもの | ①未支給の失業等給付 |
遺族基礎年金とは何か?
国民年金の被保険者や被保険者であった方が、原則として昭和61年4月1日以後にお亡くなりになった場合、その遺族に対して支給される年金です。
どのような方が亡くなった場合に、遺族基礎年金が支給されるのか?
1.国民年金の被保険者
2.国民年金の被保険者であった者で、日本に住所がある60歳以上65歳未満の方
3.老齢基礎年金を受けている方
4.老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている方
上記の1~4の条件を満たす方がお亡くなりになった場合に支給されます。
遺族基礎年金の支給条件
ただし、上記の1と2の方は、お亡くなりになった月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、保険料を納めていた期間と保険料を免除されていた期間が被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
(平成38年4月1日より前にお亡くなりになった方で65歳未満の方には軽減措置があります。)
遺族基礎年金が支給される遺族
支給対象は、お亡くなりになった当時、国民年金の被保険者等に生計を維持されていて、一定の条件を満たした子と配偶者に限られます。
1.子の条件➡「18歳になった年の年度末までの子で独身であること」又は「20歳未満であって障害等級1級・2級の障害状態にある子」で独身であること
2.配偶者の条件➡遺族年金を受けることのできる子と生計を同じくすること
遺族基礎年金の支給額(平成28年度の場合)
1.子に対する支給額(子の人数によって加算されます。)
| 子の数 | 遺族基礎年金の額 |
| 1人 | 780,900円 |
| 2人 | 780,900円+224,700円 |
| 3人 | 780,900円+224,700円+74,900円 |
| 4人 | 780,900円+224,700円+74,900円×2 |
※上記の額を子の人数で割った額が、子1人分の支給額になります。
2.配偶者に対する支給額(生計を同じくする子の数によって加算されます。)
| 生計を同じくする子の数 | 遺族基礎年金の額 |
| 1人 | 780,900円+224,700円 |
| 2人 | 780,900円+224,700円×2 |
| 3人 | 780,900円+224,700円×2+74,900円 |
| 4人 | 780,900円+224,700円×2+74,900円×2 |
※配偶者が遺族基礎年金の支給を受ける場合、子には支給されません。
寡婦年金とは何か?
夫が国民年金から、老歴基礎年金を受ける前にお亡くなりになった場合に、一定の条件を満たす妻に支給される年金です。妻が60歳から65歳になるまで最大で5年間支給されます。なお、妻が亡くなった場合でも夫には支給されません。
寡婦年金が支給されるための夫の条件
寡婦年金が支給されるためには、お亡くなりになった夫が次の条件を満たしている必要があります。
1.夫の死亡日の前日の時点で、死亡月の前月までに国民年金の老齢基礎年金の受給資格(第1号被保険者として保険料を納めていた期間と免除されていた期間を合わせて25年以上)を満たしていること
2.国民年金の障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
3.国民年金の老齢基礎年金が支給されていないこと
寡婦年金が支給されるための妻の条件
寡婦年金が支給されるためには、お亡くなりになった夫だけでなく妻も次の条件を満たしている必要があります。
1.夫がお亡くなりになった当時、夫によって生計を維持されていたこと
2.婚姻期間が10年以上あること
3.65歳未満であること
4.国民年金の老齢基礎年金が支給されていないこと
寡婦年金の年金額
年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の額の4分の3です。
この老齢基礎年金の額は、夫の死亡月の前月までの第1号被保険者としての保険料を納めた期間と保険料が免除された期間をもとに計算されます。
死亡一時金とは何か?
国民年金保険料を納めていたにもかかわらず、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前にお亡くなりになった場合に、遺族に支給される一時金です。保険料の掛け捨てを防止するための制度です。
死亡一時金が支給されるための条件
死亡一時金が支給されるためには、お亡くなりになった方が次の条件を満たしている必要があります。
1.死亡日の前日において、死亡月の前月までに国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間が36か月以上あること
2.国民年金の老齢基礎年金の支給を受けたことがないこと
3.国民年金の障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
死亡一時金が支給される遺族
お亡くなりになった方の死亡の当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これ以外の遺族には支給されません。
死亡一時金が支給される遺族の順位
死亡一時金が支給される遺族には次の順位があります。
| 第1順位 | 配偶者 |
| 第2順位 | 子 |
| 第3順位 | 父母 |
| 第4順位 | 孫 |
| 第5順位 | 祖父母 |
| 第6順位 | 兄弟姉妹 |
※先の順位の遺族がいればその方に支給され、後の順位の方には支給されません。
死亡一時金の額
死亡一時金の額は、死亡月の前月までの第1号被保険者期間のうち、死亡日の前日の時点における保険料を納めた月数によって次のように金額が定められています。
| 国民年金保険料を納付した月数 | 死亡一時金の額 |
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
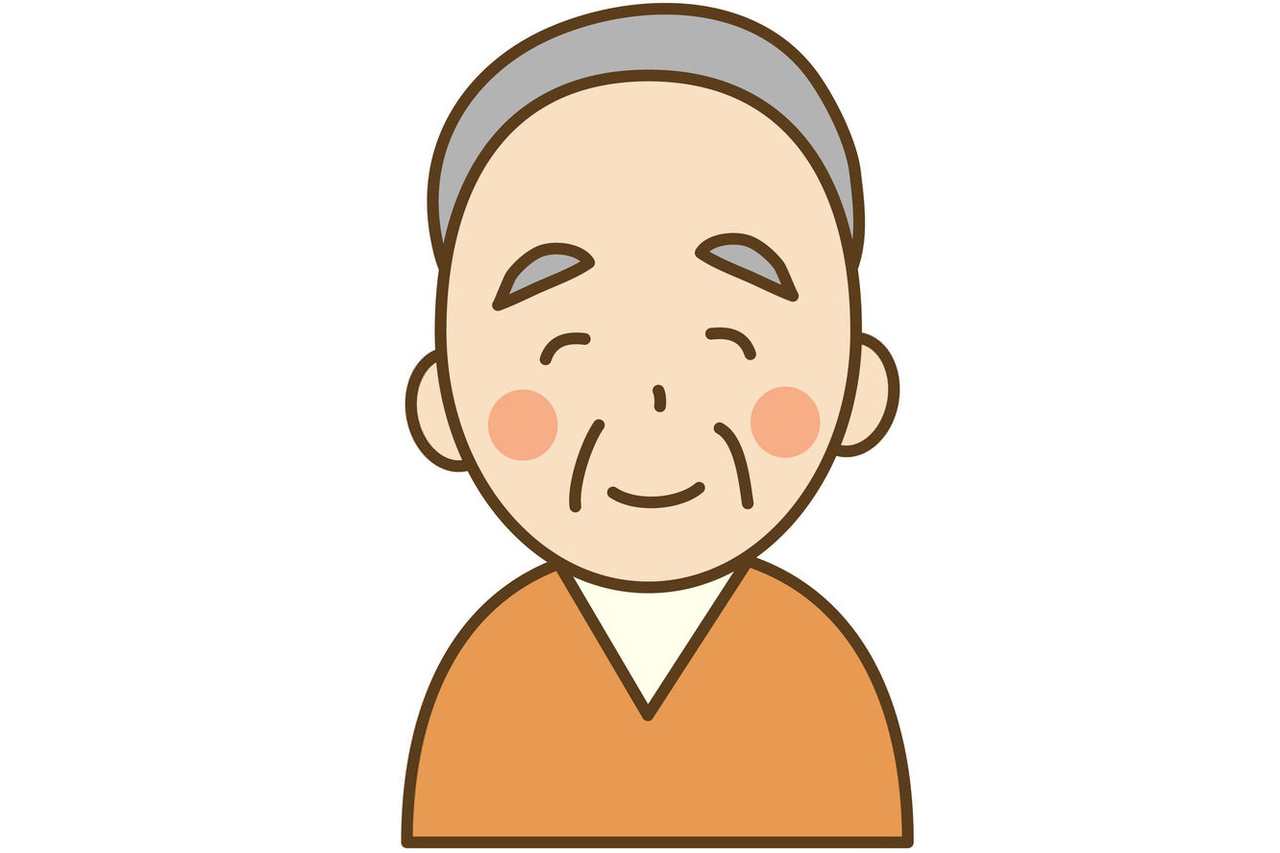
遺産分割と厚生年金について
お亡くなりになった方が、一定の条件を満たせば一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金も相続財産ではないので、遺産分割の対象になりません。
こちらでは、厚生年金から遺族に支給される遺族厚生年金についてご紹介いたします。なお、厚生年金からは、国民年金のように寡婦年金や死亡一時金の支給はありません。
遺族厚生年金とは何か?
厚生年金の被保険者又は被保険者であった方が、お亡くなりになった場合に、その遺族に対して支給される年金です。
どのような方が亡くなった場合に、遺族厚生年金が支給されるのか?
1.厚生年金の被保険者
2.厚生年金の被保険者であった方で、被保険者であった間に初診日がある病気等によって、その初診日から5年を経過する前に亡くなられた方
3.1級又は2級の障害厚生年金を受けている方
4.老齢厚生年金を受けている方又は老齢厚生年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている方
遺族厚生年金の支給条件
上記の1と2の方は、お亡くなりになった月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、保険料を納めていた期間と保険料を免除されていた期間が被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
(平成38年4月1日より前にお亡くなりになった方で65歳未満の方には軽減措置があります。)
遺族厚生年金が支給される遺族
支給対象は、お亡くなりになった方の死亡の当時にその方と生計を同じくしていて、次の条件を満たす配偶者、子、父母、祖父母、子、孫に限られます。
ただし、年収が850万円以上ある遺族には支給されません。
また、兄弟姉妹には遺族厚生年金は支給されません。
| 妻の条件 | 亡くなった方と生計を同じくしていたこと |
| 夫の条件 | 亡くなった方と生計を同じくしていたこと+年齢が55歳以上 |
| 父母・祖父母の条件 | 亡くなった方と生計を同じくしていたこと+年齢が55歳以上 |
| 子・孫の条件 | 亡くなった方と生計を同じくしていたこと + 18歳になった年の年度末までの方で独身であること 20歳未満であって障害等級1級・2級の障害状態にある方で独身であること |
遺族厚生年金が支給される遺族の順位
遺族厚生年金が支給される遺族には次のように順位があります。先の順位の方が支給をうけることができる場合、後の順位の方には遺族厚生年金は支給されません。
また、子が20歳以上になった場合など、先の順位の方が受給資格を失っても、後の順位の方には支給されません。
| 第1順位 | 配偶者と子 |
| 第2順位 | 父母 |
| 第3順位 | 孫 |
| 第4順位 | 祖父母 |
遺族厚生年金の支給額
支給額は、お亡くなりになった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分3の額です。
したがって、遺族基礎年金とは異なり、お亡くなりになった方の勤務年数や給与額によって遺族厚生年金の額は変わってきます。
なお、お亡くなりになった方の死亡時に40歳以上あった妻で一定の条件を満たす者には、最大で遺族基礎年金額(780,900円)の4分の3の金額が加算されます。
その他メニューのご紹介
サイドメニュー
司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
住所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地
藤原マンション2−B
京都市営地下鉄
北大路駅又は北山駅
徒歩13分
京都市バス
洛北高校正門前から徒歩2分
駐車場1台分あり
営業時間
9:00〜18:30
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
休業日
土曜日・日曜日・祝日
事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。




