相続に関するご相談ならお気軽にご相談ください!
えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
営業時間 | 9:00〜18:30 |
|---|
休業日 | 土日祝 |
|---|
事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。
戸籍の見方のポイント

こちらでは戸籍の見方のポイントとして、次のことをご紹介いたします。
1.戸籍が新しく作成される場合
2.戸籍が閉鎖される場合
3.ある人が戸籍に在籍した期間の見方
4.転籍があった場合の本籍地の見方
どうぞご参考になさってください。
戸籍の見方について、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
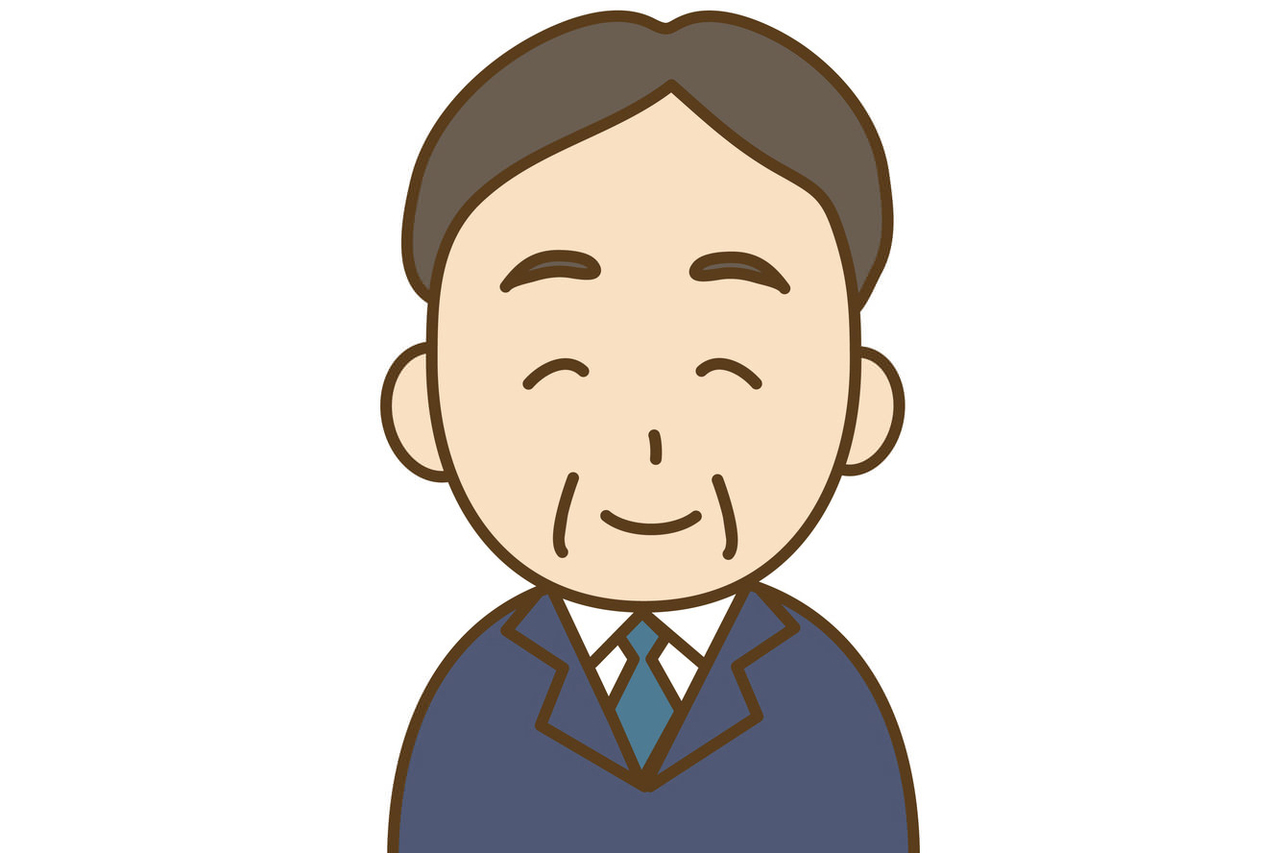
戸籍が新しく作成される場合
戦前に作成された戸籍と戦後に作成された戸籍では、戸籍が新しく作成される原因が異なります。
まず、明治31年式、大正4年式戸籍の事由からご紹介いたします。
明治31年式、大正4年式戸籍の場合
■家督相続
家督相続とは戸主を別の者に引き継ぐことをいいます。戸主が交代すると新戸主を筆頭として新しい戸籍が作成されます。
明治31年式戸籍の場合、家督相続の年月日は「戸主となりたる原因及び年月日欄」に記載されます。
大正4年式戸籍の場合、家督相続の年月日は「戸主の事項欄」に記載されます。
■分家
分家とは、ある家に属する家族が戸主の同意を得て、新たに家を設立することです。新しい家の設立によって、戸籍が新しく作られます。
■一家創立
法律で定められた原因に基づき新たに家が設立されることです。
具体的な例として嫡出でない子が、父の家にも母の家にも入れない場合などです。
■他市町村からの転籍
明治31年式、大正4年式戸籍の両方とも転籍前の本籍地と転籍の年月日が「戸主の事項欄」に記載されます。
また、転籍地で新しく作成された戸籍には除籍された者に関係するものを除いて、前の戸籍に書かれていた身分の記録や戸籍が作成された記録が全て記載されます。
そのため、新しい戸籍にはその戸籍が作成される前にあった転籍の情報や家督相続の情報が記載されていることがあります。
(他市町村からの転籍の記載例)
転籍が何度も行われている場合、戸主の事項欄に次のように記載されます。
「明治40年4月1日大阪府A市B町C番地より転籍届出同日受付入籍」
「京都府A市B町C番地より転籍届出大正5年5月1日受付入籍」
➡この記載から、明治40年4月1日に大阪府A市B町C番地から京都府A市B町C番地に転籍し、大正5年5月1日に京都府A市B町C番地から現在の本籍地に転籍したことが分かります。そして、大正5年5月1日に戸籍が新しく作成されたことが分かります。
➡つまり、この戸籍の作成年月日は「大正5年5月1日」です。
➡なお、「明治40年4月1日大阪府A市B町C番地より転籍届出同日受付入籍」は、この戸籍が作成される前の転籍情報で、この戸籍が作成された年月日とは関係ありません。
■戸籍の改製
戸籍の改製については、このサイトの別のページにある「戸籍の改製について」に詳しく記載しております。そちらをどうぞご覧になってください。
現行戸籍の場合(主な原因)
■婚姻
新しく世帯ができた場合や1つの戸籍に3世帯が在籍するような状況になる場合に、新しく戸籍を作るという考え方に基づきます。
具体例1 日本人同士の結婚
➡夫の氏を称する場合は夫が、妻の氏を称する場合は妻が筆頭者になります。
具体例2 父の戸籍に入っている娘が外国人と結婚した場合
➡娘を筆頭者とする戸籍が作成されます。
具体例3 父の戸籍に入っている娘が結婚していない状態で子供を生んだ場合
➡娘を筆頭者とする戸籍が作成されます。
■分籍
■他市町村からの転籍
■戸籍の改製
現行戸籍の場合、コンピューター化された時に改製が行われています。

戸籍が閉鎖される場合
戸籍が閉鎖されることを消除といいます。
消除された戸籍を除籍といいます。また、改製によって消除された戸籍を改製原戸籍といいます。
戸籍が消除される原因は、戦前戸籍と現行戸籍とで違いがあります。
ここでは、相続でよく使われる明治31年式戸籍・大正4年式戸籍・現行戸籍が消除される場合についてご紹介いたします。
明治31年式戸籍・大正4年式戸籍が消除される場合
■家督相続
戸主が交代すると前の戸主の戸籍は消除されます。
消除された年月日と家督相続により消除する旨は、戸主の事項欄に記載されます。
■廃家
戸主が家を消滅させることです。家に在籍していた者は他の家に入ることになります。
■絶家
家督相続が開始したが、その家に家督相続人がいないために家が消滅することです。
■他の市町村への転籍
他市町村へ転籍すると転籍先で新しい戸籍が作成され、転籍前の戸籍は消除されます。
明治31年式、大正4年式戸籍の両方とも転籍後の本籍地、転籍の年月日、転籍によって戸籍が消除された旨が「戸主の事項欄」に記載されます。
■戸籍の改製
改製によって戸籍を新しく作り直すと、それまでの戸籍は不要となり消除されます。明治31年式、大正4年式戸籍の両方とも改製の年月日、改製によって戸籍が消除された旨が「戸主の事項欄」に記載されます。
現行戸籍が消除される場合
■戸籍の全員が死亡や婚姻によってその戸籍から除かれた場合
■他の市町村への転籍
■戸籍の改製

ある人が戸籍に在籍した期間などの見方
戸籍の存続期間の見方
戸籍が作成されてから削除されるまでの期間が戸籍の存続期間です。
したがって、戸籍の存続期間は、戸籍が作成された年月日と削除された年月日を見れば分かります。
ある人物が戸籍に入籍した時期の見方
ある人物が戸籍に入籍した時期を探す場合、明治31年式戸籍と大正4年式戸籍では、対象者の名前の上にある戸籍事項欄をチェックします。
また、現行戸籍では対象者の名前の上にある身分事項欄をチェックします。
具体的には、次のとおりです。
1.ある人物が戸籍に入籍する主な原因は、出生、婚姻、養子縁組です。
2.明治31年式戸籍と大正4年式戸籍では、対象となる人物の氏名の上にある戸籍の事項欄に出生、婚姻、養子縁組の年月日、その戸籍に入籍する前の本籍地の情報が記載されます。
3.現行戸籍では、対象者の氏名の上にある戸籍の身分事項欄に出生、婚姻、養子縁組の年月日、その戸籍に入籍する前の本籍地の情報が記載されます。
4.現行戸籍がコンピューター化された後の戸籍には、出生の情報や養子縁組の情報は記載されますが、コンピューター化される前の婚姻や前の本籍地の情報は記載されません。
それぞれの具体的な記載例は次のとおりです。
明治31年式戸籍・大正14年式戸籍の記載例
対象者となる人物の名前の上にある戸籍の事項欄に次のように記載されます。
■出生の場合
「滋賀県A市B町C番地において出生父甲野太郎届出大正5年5月1日受附入籍」
➡この場合、大正5年5月1日に滋賀県A市B町C番地において出生したことを意味します。そして、父の甲野太郎が戸主であれば、同じ日に甲野太郎の戸籍に入籍したことを意味します。
■婚姻の場合
「滋賀県A市B町C番地戸主甲野太郎妹大正5年5月1日乙野次郎と婚姻届出同日入籍」
➡この場合、大正5年5月1日に甲野太郎の妹である人が乙野次郎と婚姻して本籍地が滋賀県A市B町C番地の戸籍から、結婚当時、乙野次郎の属する戸籍に入籍したことを意味します。
■養子縁組の場合
「滋賀県A市B町C番地戸主甲野太郎と養子となる縁組届出昭和5年5月1日受附入籍」
➡この場合、昭和5年5月1日に甲野太郎と養子縁組をし、本籍地が滋賀県A市B町C番地の甲野太郎の戸籍に入籍したことを意味します。
現行戸籍の記載例
対象者の人の名前の上にある戸籍の身分事項欄に次のように記載されます。
1.コンピューター化される前の現行戸籍の場合
■出生の場合
「昭和30年5月1日滋賀県A市B町C番地で出生父甲野太郎届出同月同日受附入籍」
➡この場合、昭和30年5月1日に滋賀県A市B町C番地で出生し、父の甲野太郎が戸主又は筆頭者であれば、同じ日に甲野太郎の戸籍に入籍したことを意味します。
■婚姻の場合
「昭和30年5月1日甲野太郎と婚姻届出滋賀県A市B町C番地乙野次郎戸籍より入籍」
➡この場合、昭和30年5月1日に甲野太郎と婚姻し、本籍地が滋賀県A市B町C番地の乙野次郎の戸籍から、結婚当時、甲野太郎が属していた戸籍に入籍したことを意味します。
■養子縁組の場合
「甲野太郎の養子となる縁組届出昭和30年5月1日受附滋賀県A市B町C番地
乙野次郎戸籍より入籍」
➡この場合、昭和30年5月1日に甲野太郎の養子となり本籍地が滋賀県A市B町C番地の乙野次郎の戸籍から甲野太郎の戸籍に入籍したことを意味します。
2.コンピューター化された後の現行戸籍の場合
■出生の場合
「出生日」昭和30年5月1日 「出生地」滋賀県A市
「届出日」昭和30年5月5日 「届出人」父
「送付を受けた日」昭和30年5月5日 「受理者」滋賀県A市長
➡この場合、昭和30年5月1日に出生したことを意味します。父が戸主又は筆頭者であれば、昭和30年5月5日に父の戸籍に入籍したことを意味します。
■婚姻の場合
「婚姻日」平成5年5月1日
「配偶者氏名」甲野太郎
「従前戸籍」滋賀県A市B町C番地 乙野次郎
➡この場合、平成5年5月1日に婚姻して、前に入っていた乙野次郎の戸籍を出て、甲野太郎の戸籍に入ったことを意味します。
➡なお、戸籍がコンピューター化される前に離婚していた場合、コンピュータ化されて新しく作られた戸籍には、離婚に関する記録は記載されません。
■養子縁組の場合
「縁組日」昭和30年5月1日
「養父(母)氏名」甲野太郎
「養親の戸籍」滋賀県A市B町C番地 甲野太郎
➡この場合、昭和30年5月1日に養子縁組をして、前に入っていた戸籍を出て、甲野太郎の戸籍に入ったことを意味します。
ある人がその戸籍から除籍した時期の見方
ある人が、戸籍から除籍された時期を見る場合、明治31年式戸籍と大正4年式戸籍では、対象者の名前の上にある戸籍事項欄をチェックしてください。
また、現行戸籍では対象者の名前の上にある身分事項欄をチェックしてください。
具体的には、次のとおりです。
1.ある人が戸籍から除籍する主な原因は、婚姻・養子縁組・死亡です。
2.明治31年式戸籍と大正4年式戸籍で婚姻・養子縁組があった場合、対象者の氏名の上にある「戸籍の事項欄」に「婚姻・養子縁組の年月日」・「その戸籍から除籍される旨」・「入籍する新しい戸籍の本籍地と相手の名前」が記載されます。
3.明治31年式戸籍と大正4年式戸籍で死亡があった場合、対象者の氏名の上にある「戸籍の事項欄」に「死亡した年月日」・「その戸籍から除籍される旨」「死亡した場所」が記載されます。
➡つまり、明治31年式戸籍と大正4年式戸籍では、対象者の氏名の上に記載された内容をチェックすればよいということです。
4.現行戸籍で婚姻・養子縁組があった場合、対象者の氏名の上にある「身分事項欄」に「婚姻・養子縁組の年月日」・「その戸籍から除籍される旨」・「入籍する新しい戸籍の本籍地と相手の名前」が記載されます。
5.現行戸籍で死亡があった場合、対象者の氏名の上にある「身分事項欄」に「死亡した年月日」、「死亡によりその戸籍から除籍される旨」、「死亡した場所」が記載されます。
➡つまり、コンピューター化される前の現行戸籍では、対象者の氏名の上に記載された内容をチェックすればよいということです。
6.現行戸籍がコンピューター化された後の戸籍には、対象者の氏名の下にある「身分事項欄」にコンピューター化された後の婚姻・養子縁組・死亡の情報は記載されます。
➡ただし、コンピューター化される前の婚姻や死亡の情報は記載されません。
➡コンピューター化される前の養子縁組の情報は記載されます。
同じ市町村内で転籍があった場合の本籍地の見方
同じ市町村内の転籍があった場合、新しく戸籍は作られません。そして、戸籍の記載が次のように訂正されます。
■明治31年式戸籍、大正4年式戸籍の場合
1.本籍欄の前の本籍地を線で抹消し、その横に転籍後の本籍が記載されます。
2.戸主の事項欄に転籍先の本籍と転籍日が記載されます。
■コンピューター化される前の現行戸籍の場合
1.本籍欄の前の本籍地を線で抹消し、その横に転籍後の本籍が記載されます。
2.戸籍の事項欄に転籍後の本籍と転籍日が記載されます。
■コンピューター化の後の現行戸籍の場合
1.本籍欄に転籍後の本籍が記載されます。
2.戸籍事項欄に転籍日と転籍前の本籍地が記載されます。
他の市町村へ転籍があった場合の本籍地の見方
他の市町村へ転籍があった場合、新しく戸籍が作られ、前の戸籍は除籍(閉鎖のこと)されます。そして、前の戸籍と新しく作られた戸籍の記載は次のようになります。
■明治31年式戸籍、大正4年式戸籍の場合
1.前の戸籍に記載される事項
(1)「戸主の事項欄」に転籍先と転籍により削除する旨が記載されます。
(2)「本籍欄」の右上に「除籍」と記載されます。
2.新しい戸籍に記載される事項
(1)「戸主の事項欄」に転籍前の本籍と転籍日が記載されます。
(2)「本籍欄」に新しい本籍地が記載されます。
(3)前の戸籍に記載されていた人の身分事項は、婚姻・養子縁組・死亡などにより除籍された者以外を除いて、新しい戸籍の「身分事項欄」に記載されます。
(4)前の戸籍に記載されていた戸籍の編製事項(戸籍の作成理由や作成日)は新しい戸籍の「戸主の事項欄」に記載されます。
➡つまり、新しい戸籍の「戸主の事項欄」には、転籍前の戸籍の作成日も記載されるため、この日を新しい戸籍の作成日と勘違いしないように注意が必要です。
■コンピューター化される前の現行戸籍の場合
1.前の戸籍に記載される事項
(1)「戸籍事項欄」に転籍先と転籍により削除する旨が記載されます。
(2)「本籍欄」の右上に「除籍」と記載されます。
2.新しい戸籍に記載される事項
(1)「戸籍事項欄」に転籍前の本籍と転籍日が記載されます。
(2)「本籍欄」に新しい本籍地が記載されます。
(3)転籍の時点で前の戸籍に在籍する者のみを新しい戸籍に記載します。
➡なお、前の戸籍に記載されていた戸籍の編製事項(戸籍の作成理由や作成日)は新しい戸籍には記載されません。
(昭和23年~昭和35年までに新しい戸籍が作成された場合を除きます。)
■コンピューター化された後の現行戸籍の場合
1.前の戸籍に記載される事項
(1)「戸籍事項欄」に転籍先と転籍日が記載されます。
(2)「本籍欄」の左上に「除籍」と記載されます。
2.新しい戸籍に記載される事項
(1)「戸籍事項欄」に転籍前の本籍と転籍日に記載されます。
(2)「本籍欄」に新しい本籍地が記載されます。
(3)転籍の時点で前の戸籍に在籍する者のみを新しい戸籍に記載します。
その他メニューのご紹介
主な相続手続きの方法

主な相続手続きの方法ついて説明しております。
(現在、作成中です)
遺留分とは何か?

遺留分について説明しております。
(現在、作成中です)
相続を放棄する方法

相続を放棄する方法について説明しております。
(現在、作成中です)
サイドメニュー
司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
住所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地
藤原マンション2−B
京都市営地下鉄
北大路駅又は北山駅
徒歩13分
京都市バス
洛北高校正門前から徒歩2分
駐車場1台分あり
営業時間
9:00〜18:30
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
休業日
土曜日・日曜日・祝日
事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。

